KOKUBA
JIDOUKAN
国場児童館

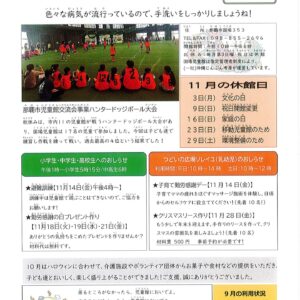
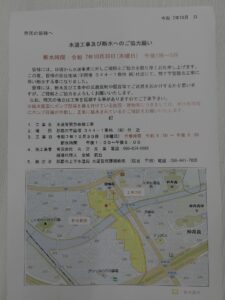


| 所在地 | 那覇市字国場353番地 |
| 開館時間 | 午前10時から午後6時まで |
| 休館日 | 毎月第三日曜日、国民の祝祭日(子どもの日は開館)、慰霊の日、年末年始(12月29日~1月3日) |
0歳~18歳までの児童に対して、遊びをとおして異年齢も含めた人間関係を学び、友達の輪を広げていく。
行事やイベントなど様々な体験を通して、情操を豊かに育てる。
つどいの広場事業などを通して、乳幼児の親子が集い、保護者同士の交流と子育てを楽しむ場を提供し、相談にも対応し地域の子育てを支える。
児童をとおした食支援の取り組みを行うなど、家庭の抱える課題を見守り、必要な場合は公的支援へとつなぐ。
那覇市国場児童館では、子どもたちが安心して過ごせる「居場所づくり」を大切にしています。
遊びを通して自然に友達ができ、自己表現の場が広がります。年齢や個性に応じた多様な遊びの中で、
子どもたちがのびのびと成長できる環境を提供します。誰もが「自分らしくいられる場所」として、
地域の子どもたちを見守り、支え続けていきます。
子ども・親子の利用施設ですが、利用の第一歩のハードルを下げるために、必要な方に届くための情報発信、安心して利用できる環境づくり、保護者との関係づくりに取り組みます。

子どもたちの日常を充実させる遊びを提供するだけでなく、話し相手となり、友達づくりや地域と関わる機会を提供し、子どもの成長に必要な大人の関わりを豊かにしていきます。

児童館という子どもが日常的に利用する施設のため、福祉的困窮対策としてではなく、子どもの健全育成の視点で、人間関係を大事にした食事の機会づくり、「ご近所からのおすそ分け」のように、保護者との関係を大切にした見守りの手段として食支援を行います。

工作、運動、料理など、生活の中で役立つ体験の場と、遠足や地域活動など、思い出作りや社会経験につながる体験の場づくりに取り組み、体験を消費させるのではなく、生きる力につながる体験の蓄積ができるように取り組みます。

子どもの生活環境には、関係性や経済的貧困、保護者の長時間労働、ヤングケアラーなど、
子どもの育ちに影響を与える要因があります。その様な中だからこそ、日々の会話や関わりをとおして、
子どもと大人が信頼関係を築き、困りごとを話し合えるようにすることを大切に運営します。
そのうえで、地域の事業所と連携した行事を行うことで地域の皆さんにも関係をつなげ、
体験をとおして様々な思い出を作り、自分らしさを育てられる環境を作ります。
また、日頃の付き合いの中で福祉的課題を見つけた際は適切な支援機関につないだり、
食育活動の一環としての食支援などを行い、助ける↔助けられる関係ではなく、
見守る↔必要な時は手伝うといった、関係が豊かになることを目指して、支援に取り組んでいきます。


| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 活動曜日 | 火曜・水曜・金曜 |
| 活動時間 | 10時~14時 |
| 活動内容 | 子育て中の保護者の交流、情報交換の場を提供し、定期的な講座の実施などを通して、子育て支援を行う。 |

この様な考えをもとに、子どもの日常を大切にする関わりをベースに、地域の方々と一緒に取り組む活動を増やすように意識し、第二期指定管理期間は取り組みました。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大という、未曾有の事態が発生。子どもたちの日常の行動制限が強く行われるなど、緊急事態の中で、子どもの権利の侵害が許容される状況が続きました。新型コロナウイルスの感染拡大以降、子どもの自殺、引きこもりや不登校などの児童も増加しました。国場児童館を利用していた児童や家庭にも、虐待や貧困状態など、様々な困窮状況が発生したため、民生委員やフードバンク、那覇市社会福祉協議会のCSWと連携を強化し、気になる家庭への見守り支援を行う等の対応を続けてきました。
この様な子どもの状況を改善し、子どもの権利が尊重される社会の実現を目指して、令和4年12月には、県内外の子ども支援団体と連携した行事、「子どもの権利条約フォーラムin那覇/沖縄」を開催。玉城デニー沖縄県知事をはじめ、延べ1,500人が参加し、子どもの権利が守られる社会づくりについての学びを深める機会を創出しました。この行事を通し、子どもの権利条約の理念を広めることには一定程度の成果はありましたが、社会の状況はまだ変わっていないため、那覇市における子どもの権利条例の制定に向けた子どもの参加など、児童館としても積極的に取り組んでいくことが必要です。
那覇市からの運営引継ぎ以降、子どもたちの今に寄り添う児童館を目指し、毎日の関わりを大切にした「ふるさとのような居場所づくり」に取り組んできました。密な関わりを重視し、子どものニーズに合わせた環境整備を行っています。
行政・学校・地域団体などとの連携を深め、虐待や困窮家庭への見守り支援も実施してきました。特にコロナ禍以降は民生委員やフードバンク、CSWと協力し、子どもと家庭の安心を守る活動を継続しています。情報発信にも努め、地域の理解と参画を促進してきました。
行事やイベントを通して子どもの情緒を育む一方、令和4年には「子どもの権利条約フォーラムin那覇/沖縄」を開催。1,500人が参加し、県内外の支援団体と連携して子どもの権利を考える機会を創出しました。今後も条例制定に向け、子どもの声が活かされる社会を目指して活動を続けていきます。

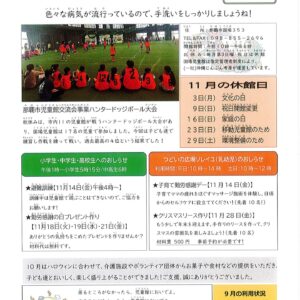
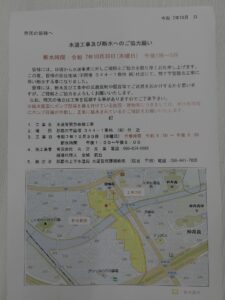
公共施設の運営や地域体験学習、子どもたちが
のびのびと過ごせる日常を支えるための活動に
ご関心がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。